SNSのダイエットアカウントなどで一度は「PFCバランス」という言葉を目にしたことはないでしょうか。
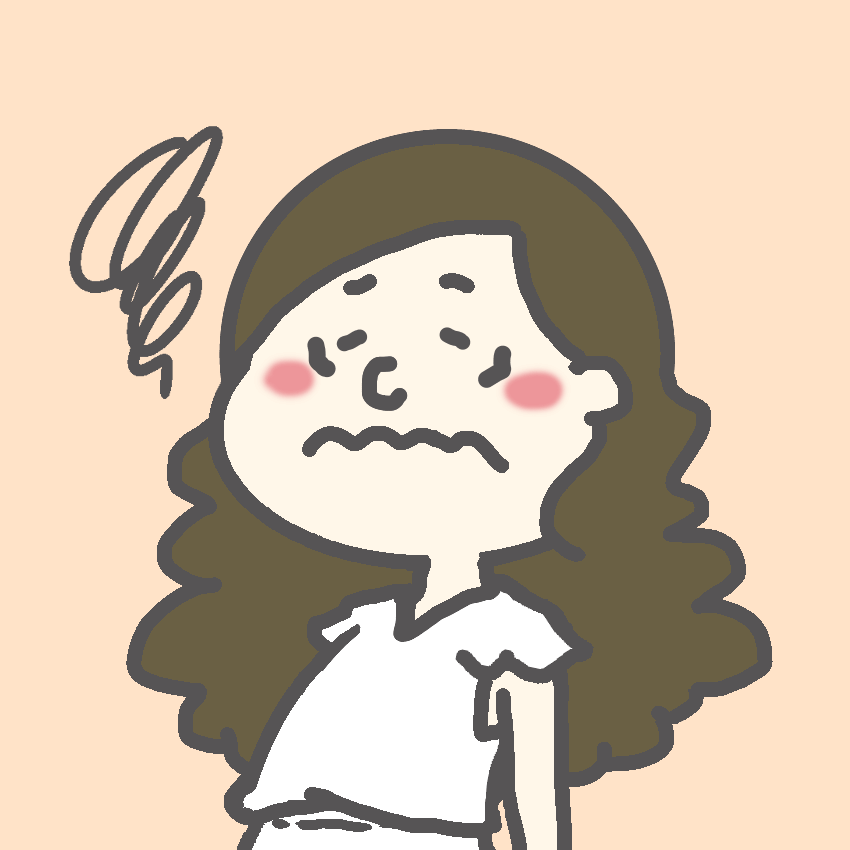
あるけどPFCってそもそも何なの・・・
私もダイエット検定を勉強するまではきちんと分かっていませんでした。
というのも、そもそもダイエット(diet)という単語が英語では「日常の食事」の意味であることからもわかるように、実際ダイエットの9割が食事と言われているほど食事が大事だからです。
ただ単に体重を落とすだけならPFCバランスを気にせずにただ摂取カロリーを減らすだけでもある程度は可能ですが、その際脂肪だけではなく筋肉も一緒に落ちるので、代謝が悪くなり前よりも太りやすい体になります。
なので代謝を落とさずになるべく脂肪のみを落とすためには、ある程度のカロリーを摂取し、かつ筋肉の素材となるたんぱく質もきちんと取る必要があります。
その際の必要なタンパク質や脂肪・炭水化物の摂取のバランスの目安となるのがPFC計算です。
一度これを計算してみて自身に必要なPFCバランスを知っていると、ダイエットの際の食事でもどんなものをどのくらい食べれば良いか、またはどんなものを避けるべきかが具体的にわかります。
またこの記事では実際に日常でのPFC計算の取り入れ方のコツも紹介しています。
ダイエットをに挑戦中の方や、PFC計算に興味のある方は参考にしてみてください。
- PFCとは何か
- PFC計算の仕方
- PFC計算の日常での取り入れ方のコツ
それでは早速見てみましょう。
PFC とは何か
まずそもそも「PFC」とは何か。
簡単に説明すると以下の通りです。
「P」は「たんぱく質」(Protein)
「F」は「脂質」(Fat)
「C」は「炭水化物」(Carbohydrate)
これらは三大栄養素と呼ばれているもので、それぞれの頭文字をとって「PFC」と呼ばれています。
どれも身体においてそれぞれ異なった重要な役割を果たしているため、どれかが著しく欠けると健康に影響が出る場合があります。
- タンパク質
-
筋肉や血管や内臓、皮膚や髪などの主成分。これが不足すると筋肉が衰えたり、体調を崩しやすくなる。
- 脂質
-
細胞膜やホルモンの原料。体温を保つ働き。
- 炭水化物
-
筋肉や脳のエネルギー。脳の唯一の栄養素。炭水化物が不足すると足りないエネルギーを補うために筋肉を分解する。
以上のようにそれぞれ重要な役割のある栄養素なので、ダイエットにおいてもこれらをバランス良く取ることが重要です。
ダイエットといえば「糖質制限」で極端に炭水化物をとらないようにしている人もいますが、長期的に見れば身体に良くないのでできればやめましょう。
PFCバランスの計算の仕方
では次にPFCバランスの計算の仕方です。
PFCのバランスの設定は、その人の体重や年齢・また身体の状態や1日の活動量によって異なり、またその設定の仕方にもまだ様々な見解があります。
厚生労働省で推奨されている比率は以下の通りです。
| たんぱく質 | 13~20% |
| 脂質 | 20~30% |
| 炭水化物 | 50~65% |
このバランスで計算は以下で紹介します。
✳︎計算の参考例は体重53kg体脂肪率23%で計算します。
体重(kg)×体脂肪率(%)=体脂肪の重さ(kg)
たとえば体重53kg・体脂肪率23%の場合
53(kg)×0.23(23%)=12.19(kg)
体脂肪は%を100で割って数値化してね。(23÷100=0.23)
体重(kg)-脂肪の重さ(kg)=除脂肪体重(kg)
先ほどの例の場合
53(kg)-12.19(kg)=40.81(kg)
1日の活動量によっても異なりますが、ここでは通常の目安として1kgあたり40kcalで計算します。
除脂肪体重×40(kcal)=1日の摂取カロリー目安(kcal)
先の例だと
40.81(kg)×40(kcal)=1632.4(kcal)
つまり体重53kg体脂肪率23%の人の1日の摂取カロリー目安は1,632kcalということです(小数点切り捨て)
1日の摂取カロリー目安(kcal)×13~20%(Pの割合)=1日のたんぱく質の量(kcal)
先の例でそれぞれ計算すると
1632(kcal)×0.13(13%) ~0.20(20%)=326.4(kcal) = 212~326(kcal)
なので1日のたんぱく質摂取量は212~326kcalです。
1日の摂取カロリー目安(kcal)×20~30%(Fの割合)=1日の脂質の量(kcal)
1日の摂取カロリー目安(kcal)×50~65%(Cの割合)=1日の炭水化物の量(kcal)
先の例でそれぞれ計算すると脂質は
1623(kcal)×0.20~0.30(20~30%)=324~486(kcal)
炭水化物は
1623(kcal)×0.50~0.65(50~65%)=811~1054(kcal)
たんぱく質は1gあたり4kcal
脂質は1gあたり9kcal
炭水化物は1gあたり4kcal
なので
1日のたんぱく質量(kcal)÷4=1日のたんぱく質量(g)
1日の脂質(kcal)÷9=1日の脂質量(g)
1日の炭水化物量(kcal)÷4=1日の炭水化物量(g)
なので先の例だと
P : 212~326(kcal)÷4=53~81(g)
F : 324~486(kcal)÷9=36~54(g)
C : 811~1054(kcal)÷4=202~263(g)
となります。
PFC計算の日常への取り入れ方のコツ
計算が面倒な人にオススメの計算ツール
とはいえ、以上のように計算するのは結構面倒ですよね・・・
そこでいいツールを探しまくった結果、自身の年齢・身長・体重を入力するだけで導き出していくれる優秀な計算ツールを見つけたので下記にリンクを貼っておきます。
このサイトの計算では1日の活動量や減量目標から計算してくれるのでとても楽です。
また減量スピードも無理な設定をするときちんと警告が出てくれるのも安心してオススメできる理由の一つです。
PFC計算にオススメのアプリ
またスマホのカロリー計算のアプリを使うのもオススメです。
「あすけん」や「カロリーママ」「FatSecret」あたりが使ってみたところ良さそうです。
これらも身長体重や減量目標を入れると、1日に摂取したい食事のバランスや具体的な数値を教えてくれます。
そして食べたものを入力・もしくは写真を撮ると勝手に計算してくれるので、実際の計算と記録にとても便利です。
私も全部使ってみましたが、一番使いやすかったのは「FatSecret」でした。
シンプルでとても使い勝手が良かったです。
「あすけん」や「カロリーママ」も使っている人も多いので、ぜひ色々試してみて自分に合うものを見つけてみてください。
PFC計算の取り入れ方のコツ
とはいえこのPFC計算は、日々食べた物の記録するを必要があるので実際きちんとダイエットに取り入れるのは結構大変です。
しかし、いくつかコツを押さえればグッと楽に日常に取り入れることができるのでそのコツを紹介したいと思います。
- 厳密に気にしすぎない
- この計算が全てと思わない
- 食べ過ぎた日があっても焦らない
- ずっと計算し続ける必要はない
- アプリで計算記録する
カロリー計算やPFCバランスを計算していると、ついつい細かいところまで気にしすぎてしまったりしてストレスがたまってしまうこともあります。
しかし、そもそもカロリー計算自体厳密に行うことが難しいことを頭に入れておきましょう。
というのも、同じ食品でも季節や保管方法によって栄養素が変わってきたり、調理法によってカロリーが変わったりするからです。
それに毎回の食事をg単位まで測って食べていたら、それこそノイローゼになりかねません。
もちろん、一度ご自分にとっての適量を知るためにご飯の重さを測ったりするのも有効です。
しかし、何度か計っていれば大体このお茶碗にどのくらいのご飯の量なんだなというのが分かってくるので、一生ご飯を食べるたびに測る必要はないのです。
むしろ厳密にこだわりすぎると、達成できなかった時や食べ過ぎてしまった時にそこでやめてしまう原因になってしまうので、大体合っていればオッケーというくらいの心持ちで挑戦しましょう。
そもそも食べるものの栄養バランスや量に向き合っているだけでもかなり偉いことをお忘れなく!
なのでまずは完璧主義になりすぎず「大体自分がどのくらい何を食べればいいのかを把握しよう」くらいにの気持ちで始めて見るのがオススメです。
登録されている料理も多く簡単に栄養素を計算できる上に、食事の写真から計算してくれるもの、栄養バランスについてアドバイスをくれるものもあってとても便利です。
ご自身に合う続けられる方法を探りましょう!


PFCやカロリーが表記されているものを食べる
自炊の場合は計算が大変になってしましますが、コンビニや外食ではカロリーやPFCのバランスが表記されているものも最近は多くあります。
手っ取り早くこれらを利用するのも、計算を簡単にするコツです。
コンビニ食は気になるという方には、ダイエットにもおすすめの完全食のBASE FOODなどもおすすめです。
BASE FOODいついては以下の記事を参考にしてみてください。


PFCバランスまとめ
いかがでしたか?
ダイエットや健康を維持するために自身に必要なPFCのバランスを知っておくことはとても有効なので、ぜひ一度計算してみてくださいね。
私はこのPFC計算を取り入れることで停滞期から抜けることができました。
少しでもみなさんの参考になれば幸いです。

コメント